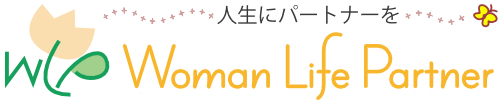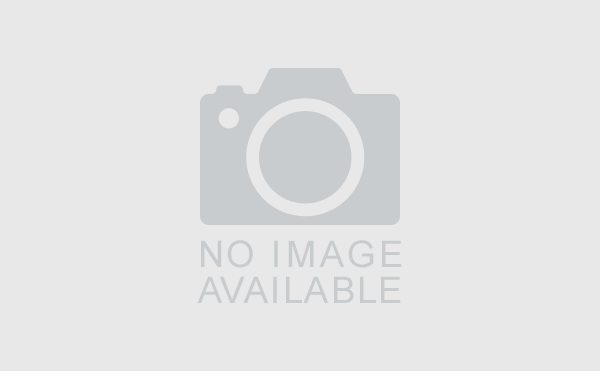【家計コラム】「関心を持ち、考え、備えよう!~国民負担率について~
今後可処分所得はどうなるの?~国民負担率について~
可処分所得とは、収入から税金や社会保険料などを除いた所得で、実際に受け取り自由に使える手取りのことです。この手取り金額が減ると家計が苦しくなります。近年は可処分所得の金額が増えていません。その原因は、所得税、住民税、社会保険料の増加等にあります。今後私達の可処分所得はどうなるのでしょうか。
まず所得税ですが、
今年度の増税は見送られたものの年収の壁123万円の引き上げと併せて今後議論されます。また近年子供の扶養控除の金額は、児童手当拡充を理由に縮小されてきました。高校生の扶養控除縮小についても引き続き議論されていくようです。基礎的な人的控除の増減は、所得は税や住民税に大きな影響があるので、注視していきたいと思います。
住民税においては、2024年度分の住民税より「森林環境税」が個人住民税均等割の枠組みを用いて課税されています。
社会保険料においては、年々増額されている上に2026年度より「こども・子育て支援金」が公的医療保険料に上乗せされることになっています。
そしてその「こども・子育て支援金」も2028年度まで増額されていきます。
社会保障給付費も高齢化に伴う増加が見込まれており、必然的に社会保険料の増加も予想されます。
社会福祉の為の税負担はやむを得ないと思いますが、このように私達の意識していないところでの増税、いわゆる「ステルス増税」が増えてくると、可処分所得は益々増えていかないのです。
では、賃金は上昇していくのでしょうか。
今年の春闘では一部の大企業の賃上げが実施されたようですが、法人税増税も予定されている中で今後の中小企業の底上げが気になるところです。
内閣府の調査によると1991年より約30年間にわたり賃金はおおむね横ばい状態となっています。(参照内閣府HP https://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je22/h06_hz020105.html)

その一方で国民負担率の推移を見てみると上がり続けています。
(参照厚労省HP https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/futanritsu/sy202402a.pdf)
国民負担率とは、公的負担の重さを示すもので、(租税負担+社会保障料負担)/国民所得で算出されます。この10年の実績値を見てみると、2012年の39.8%から2022年の48.4%となっています。

(※図は参照HPより抜粋加工)
つまり、この30年もの間、賃金が上がらない中、公的負担は近年益々増え続けているということです。働いて得た金額の約半分が税金として引かれている状態は、増税路線が変更されないかぎり続いていくと思われます。
年金制度や退職金制度、高額療養費制度等は手取りが減ったり負担が増えたりする方に向かっており、家計のやりくりが困難となってくるのは必至とも言えます。
社会保障給付費の増加や少子高齢化等様々な課題がありますが、国民にとって過度な負担とならないようしっかりと政策を検討して欲しいものです。
サポート会員 植平由美子CFPⓇ